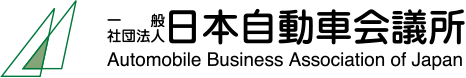税制は購買行動に多大な影響を与える。例えば、消費税前に課税されていた「物品税」。普通乗用車(3ナンバー)に23%もかかっていたこの税が1989年度の消費税導入とともに廃止されると、新車販売は約745万台と前年度比で1割も増えた。自動車税の改正もあり、高嶺の花の〝3ナンバー車〟が一気に身近になった。そして今回「自動車税環境性能割」の廃止が決まった。業界は「米国関税で苦境に立たされている自動車業界にとって、国内自動車市場の活性化や国内生産基盤の維持・強化に資する」(日本自動車工業会)と歓迎する。
環境性能割は自動車の取得時に課税される地方税だ。燃費性能などに応じ、車両取得価額の0~3%を課税し、年間2千億円の税収がある。
前身に当たる自動車取得税は1968年に創設された。もともとは「法定外普通税」(地方税法に定めがなく、総務相との協議を経て自治体が創設できる税金のうち、使途の制限がないもの)の一種として京都府や徳島県で課税されていたが、歳入全額を地方(都道府県及び市町村)の道路整備に充てる「法定目的税」として全国で課税されるようになる。
自動車ユーザーは〝贅沢税〟とも言える物品税(国税)との二重課税を消費税導入まで甘受してきた。消費税の導入で物品税は廃止されるが、取得税は「道路整備」を理由に生き残る。道路特定財源が廃止されると課税根拠がいよいよ乏しくなり、19年秋の消費増税に伴い廃止されたが、その後も看板を掛け替えることで存続してきた。
廃止の背中を押したのは〝トランプ関税〟と野党だ。自民党の税制調査会(税調)では今回、関税で苦境に立つ自動車産業を支えようと環境性能割の廃止や停止を求める意見が飛び交った。「一時的な停止では長期的な投資計画を立てられない」「駆け込み需要や反動減が生じる」と廃止を求める声も多かったが「脱炭素機運が後退する」「軽油の暫定税率廃止に続いて地方税の減収につながる」といった反対意見もあり、議論は終盤までもつれる。
税調内では高市早苗首相の「凍結発言」もあり、2年停止の方向で調整が進んでいた。しかし、与党大綱がまとまる前日、高市首相は国民民主党の玉木雄一郞代表と会談し「年収の壁」とともに環境性能割の廃止で合意。業界関係者や経済産業省が確認に追われるなど、急転直下の〝政治決着〟だった。
自動車メーカー関係者は「これだけでもわれわれにとっては大きな成果だ」と語った。しかし、税制改正大綱には「地方の減収分については、安定財源を確保するための具体的な方策を検討し、それまでの間、国の責任で手当てする」とある。税調幹部の後藤茂之小委員長代理は「ユーザーの負担軽減につながる一方、減収が生じる。受益者負担の点から、道路インフラの維持・管理に必要な財源をどうするかという議論は避けられないだろう」と話す。穴埋めの矛先が再び車体課税に向かう可能性はある。
環境性能割の廃止により、業界が長年、求めてきた自動車税制の「簡素化」は一歩前進した。新車価格が上昇基調にある中で約2千億円の減税効果に期待もかかる。一方で、今後の代替財源論を注視し、引き続き「負担軽減」を政府・与党に求めていく重要性は不変だ。