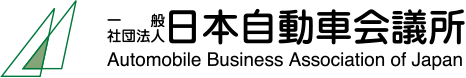2024年3月25日
日本交通科学学会 「体調起因性事故予防」シンポジウム
医学、理工学、行政などの専門家が参加し交通安全の研究を推進する日本交通科学学会(JCTS、有賀徹会長)は、日本自動車会館内のくるまプラザ(東京都港区)で「第17回交通科学シンポジウム」を開催した。今回は「体調起因性事故予防に向けた効果的なドライバーモニタリング及び運転支援技術の検討」がテーマ。運転中のドライバーに心臓疾患、てんかんの症状が発生するなど、急激な体調変化が起こった場合の安全確保について、技術開発の方向性を医学・理工学両面の視点から探った。
シンポジウムには自動車メーカーや自動車関連団体、医療関係者などが会場・オンライン合計で64人参加した。冒頭、有賀会長(労働者健康安全機構理事長)は「これから生産年齢人口(15歳以上65歳未満)が減っていくと、どうしても75歳くらいまで、ある程度働いてもらわなければならなくなるだろうが、みんな何かしらの病気を抱えている」と述べ、社会における高齢者の活躍拡大に向けて、ドライバーの体調が急変した際の安全確保が可能な運転支援技術の実現を期待するとした。
シンポジウムでは、まず医学、理工学の専門家が2人ずつ講演。医学では帝京大学医学部の三宅康史教授が救急救命、滋賀医科大学の一杉正仁教授が剖検(遺体の解剖)の実例を基に、それぞれ体調起因性事故の発生状況を解説した。
理工学では日本大学の松田礼教授が走行中の乗員の心理・生理反応の計測、諏訪東京理科大学の國行浩史教授が運転姿勢からドライバーの体調急変を検知する技術をレクチャーした。
4人の演者はパネルディスカッションに登壇し、会場・オンライン参加者の質問を受けながら、ドライバー異常検知のモニタリングについて技術の方向性を議論した。一杉教授がコーディネーターを務めた。
まず國行教授は「姿勢の検知は正常な姿勢があった上でできるものだ。ただ、着座姿勢をみるとふんぞり返る人がいたり、さまざまだ。その中で0・1秒など短時間での検知は難しい。ガイドラインでは(検知時間が)2秒以内となっているが、その姿勢を基準に異常と判断するべきか、詰めるのは至難の技だ」と、判定の難しさを示した。
松田教授は「運転は基本的には精神的な作業ととらえており、(自らの研究では)心理的・生理的な反応を測定している。運転時間の経過とともに、ストレスがかかっていくという結果も得ている。体調起因性事故の予防では、病気の発生する兆候など医学の意見をいただきながら、対策を盛り込めないかと考える」とし、医学の知見が必要だと述べた。
これを受けて三宅教授は「予防に使える可能性があると思った。普段の(心拍数などの)落ち着いた状態が分かれば(それとの比較で)異常が分かる。平熱が何度かを知ることと同じで、日頃の健康管理が大事だ。運転支援技術の開発とともに行うべきだ」とした。
これらを踏まえて一杉教授は工学の2人に「(てんかんや心臓疾患を持つ患者の)運転の可否は医者が判断しなけらばならないが、(モニタリングの可能な)運転支援装置ができれば、その装置に安全を担保させて運転してもらってもよいのだろうか」と問いかけた。
國行教授は「(現在も)体調起因性事故が起こる頻度は何百回に1回というくらい極めて少ないが、社会的にはそういう持病を抱えた人に運転はしてほしくないという意見が、現実的には多数を占めるのでは。今後の高齢化社会の課題になるだろう」と指摘した。
松田教授は「難しい問題だ、医学的な判断ができるのは工学者ではなく医者だ。例えば心電図を測定してもそれだけでは判断できない。複数のデータを組み合わせることが必要だろう。このため医学の視点をもらいながら装置の規格づくりができればと考える」と述べた。
一杉教授は「医者の判断もあるが、社会がそういう装置を信頼してくれるのかも重要になる」とし、今後も医学と理工学が連携して運転支援装置の技術開発と社会的受容性の形成に取り組み、交通安全の高度化と社会経済の発展を支えていきたいと意欲を示した。
日本交通科学学会は9月3、4日に日本大学理工学部タワー・スコラ(東京都千代田区)で「第60回学術講演会」を開催する。講演会をコーディネートする大会長は、松田教授が務める。
| カテゴリー | 交通安全,展示会・講演会 |
|---|---|
| 対象者 | 一般,自動車業界 |
日刊自動車新聞3月25日掲載