2019年9月24日
日刊自連載「どう防ぐ 高齢ドライバー事故」(4)秋田大学大学院工学研究科 水戸部一孝教授 事故の防止にVR講習を
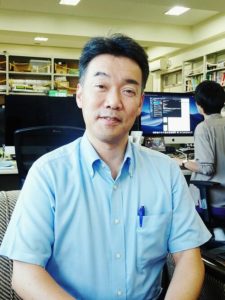
秋田大学大学院の水戸部一孝教授は、シミュレーターによる交通安全教育の研究を行っている。バーチャルリアリティー(VR)によってさまざまな道路環境を再現できるシミュレーターを高齢者の講習などに使えば、危険回避能力や、いざという時に冷静に行動するための能力を養えると話す。
―歩行者シミュレーターを使って事故の研究をされています。高齢者の特徴はどのようなものですか
「道路を渡る実験では、加齢とともに、危険な車間で道を横断する人が増えていきます。これは認知能力に問題があって、車がどれくらいの速度で接近しているのか、何秒後に到達するのかという見積もりができなくなっているということです。年齢が進むにつれ、安全な車間ですら事故率が上がることがわかります」
―なぜそのようになるのでしょうか
「視力、視野の広さ、深視力、歩行速度などの要因が影響してきます。前期高齢者では歩行速度や視野の広さは事故に関係ありませんが、後期高齢者になると関係してきます。年をとると、より軽微な衰えが事故につながりやすくなるということです。また、高齢者は自転車で車道を斜めに横断する時の事故も多い。認知・判断に時間がかかるため、車道に入った途端に後方から来る車にぶつかっています」
―死亡事故の状況が再現できるのですね
「今までは亡くなってしまっていたので、その人がどのような能力の人だったのか、知ることはできませんでした。しかし、VRによって安全な環境下で危険な状況を再現でき、事故に遭った人の属性がわかってきます。ですので、普段の認知能力テストなどの検査で少し老化が見え始めたら、こういう点を注意しないといけないといったことがわかる。事前に自分のリスク要因を知ることができれば事故防止につながるのではないかと思います」
―どのようなきっかけで交通安全の研究を始めたのですか
「もともとは人間を工学的に調べる分野で仕事をしていました。今の研究を選ぶきっかけになったのは、私が秋田大で働き始めて2カ月後に学生が交通事故で亡くなってしまったことです。事故のあった道路には人間のミスを招く要因がたくさんありました。そういう場所は全国にたくさんあります。きちんとしたエビデンスのもとに、改善を促していきたいという思いがありました」
「もう一つは高齢者が多い秋田県では高齢ドライバーの事故も問題になっていくだろうと考えていたことです。たまたまマサチューセッツ工科大(MIT)のエイジラボに研究員として行く機会があり、高齢ドライバーに関する論文を書きました。ここで使っていたのがドライビングシミュレーターです。米国では高齢ドライバーの死亡事故が多いのですが、日本は歩行者事故が多い。そこで日本に帰ってから歩行者シミュレーターをつくりました。今は自転車や車のシミュレーターに広げています」
―高齢ドライバーによる事故が社会問題になっています。どうみていますか
「実際は年間3500件の死亡事故のうちのわずかです。異常性が目立つので注目されますが、一番多いのは高齢歩行者事故であり、そこは以前と変わっていません。有効な対策が打てていないのです。シミュレーターを使った交通安全講習をやっているのですが、毎年100万人の高齢者に導入しても全員に行き渡るのに36年かかります。全員が体験できれば効果があるでしょうが、今の規模では難しいと思います」
―高齢ドライバー事故では異常性も問題視されています
「普段は正常な行動や反応ができているのだと思います。ただ、高齢者の特徴として、運転行動に別の課題がかかった時、これを『二重課題』と言いますが、この時にパフォーマンスが極端に落ちる人が結構います。もう一つ異常と思えることは、一つのことに固執することです。これが結果的にパニック状態と言えるのかもしれません。危険な状況になると身体が硬直してしまい、次の行動に切り替えられない状態です」
―そういったこともシミュレーターで再現できるのですか
「歩行シミュレーターで実験していて、車に気付いた途端に体が固まってしまい、実験が終わってもそのまま動けないお年寄りがいました。運転していても歩行者が飛び出してきた途端、全身を硬直させて、ハンドルが壊れてしまいそうな反応をする人もいます。これらは従来の認知機能検査や講習ではひっかからないケースです。こうした事例で分かるように、事故に直結するような危険な状況下での行動をきちんと測ったり訓練したりする必要があります。対策の本質は、パニックを起こさないよう適切に対処できるようにすることです」
―必要なアドバイスは一人一人違うのですね
「高齢者は個人差がものすごく大きいのです。75歳以上でも大学院生と全く変わらない成績を出す人もいれば、なぜこんなに事故に遭うのかという人もいます。個々の能力を精査し、最適な条件を出してあげることが、安心して運転を続けるために必要だと思います。今、議論されている限定免許はざっくりと年齢で区切ってしまっています。もっとオーダーメイドでつくっていければ効果的です」
―高齢者の事故をなくすには何が必要でしょうか
「短期的には啓もうですが、20年先を考えればいろいろやれる可能性があります。残念ながら今は、年をとって能力が衰えた人には社会から退場してもらいましょうという、どちらかというと排除する流れです。しかし、日本は超高齢社会の先進国なのだから、本当はそれに合ったインフラをつくるべきなのです。2040年には米国も高齢化し、10年後には中国、韓国も相当な高齢社会です。当然、今のインフラでいいはずがありません」
―技術的にどのような可能性がありますか
「インフラ側にセンサーを配置すれば、いくらでも解決策があります。歩行者が歩いていることを道路がセンシングすれば、極端な話、歩行者が渡りたい道路に横断歩道を浮かびあがらせることもできる。車が自動運転化されていれば、どこでも車は止まれます。インフラにはまだまだ進化の余地があります」
―日本の道路はクルマ優先で造られてきました
「必ず横断歩道を渡りなさい、渡らないからいけない、というのが今の風潮ですが、道路の向かい側に渡るのに100㍍も離れた横断歩道まで行くでしょうか。それは高齢者や歩行者にやさしい街とはいえません。
しかし、40年に全部が自動運転になった社会であれば可能性が広がります。その頃の通信は5G(第5世代移動通信システム)の次の6Gになっています。双方向でものすごい速度で通信できるようになる。インフラには耐久性が必要です。日本は高機能・長寿命・高信頼性の分野でリーダーシップをとることができ、海外にも輸出できるはずです。世界中が高齢化するのは目に見えている。それなのになぜ今のうちに手を打たないのでしょうか」
「自動運転技術というのはチャンスなのです。歩行者をセンシングするインフラとセットであれば劇的に事故を減らせる可能性があります。これは10年後、20年後の話ではありますが、研究は今やっていかないといけません。車だけでは限界があり、行政が責任を持って歩行者をセンシングするべきです。事故を100分の1に減らせるなら行政としてぜひやってほしいと思います」(聞き手=編集局長 小室祥子)
水戸部 一孝氏(みとべ・かずたか)1991年秋田大学鉱山学部電気工学科卒、96年北海道大学大学院工学研究科博士課程修了、秋田大鉱山学部電気電子工学科助手、98年講師。2002~03年MITエイジラボ訪問研究員。08年秋田大工学資源学部准教授、13年から同大大学院工学研究科教授。1967年10月12日生まれ、51歳。
日刊自動車新聞9月20日掲載
| 開催日 | 2019年9月20日 |
|---|---|
| カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |
| 主催者 | 日刊自動車新聞社 |
| 対象者 | 一般,自動車業界 |











