2021年1月15日
交通安全環境研究所 創立50周年迎え新たにチャレンジ
日本の安全な自動車社会の実現に必須となる車両のさまざまな基準づくりの要となってきた交通安全環境研究所(交通研、平井隆志所長)が、将来を見据えた新たな試みに乗り出している。
研究に携わるメンバーからアイデアを募り、交通研が率先して長期的な視点に立ったクルマや社会システムなどの研究活動に取り組むことで、「自ら将来をつくっていける力を身につける」(平井所長)考えだ。
昨年7月に創立50周年という大きな節目を迎えた交通研。これを契機とした新しいチャレンジを通じて、「次の50年に向けて世界をリードできる新たな交通研へ」(同)と進化を急ぐ。
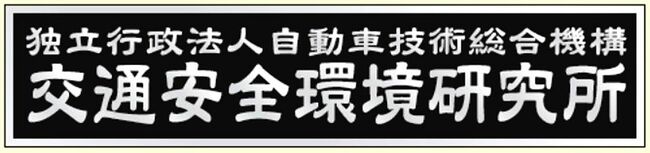
国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で昨年成立した自動運転「レベル3」関連の3つの国際基準は、いずれも日本が提唱した規格がベースとなった。
これからの世界の潮流となる自動運転技術の国際基準化で大きな存在感を示した格好だが、こうした日本の動きを支えるのも交通研だ。地道な研究の積み重ねによって精緻な技術的裏付けを示してこそ、世界が納得できる基準づくりにつながっている。
事実、国際基準となった車線維持機能でも、新たに導入した大型のドライビングシミュレーターで何度も検証を重ねながら、最も安全と考えられるものを弾き出した。
しかし、ここ最近の自動車産業については「変化が速すぎる。このスピードについていくには並大抵の体力では難しい」(同)との危機感も強める。交通研の人員体制は100人程度と、決して大きな所帯ではない。
それでも技術や環境を含め、加速度を増す変化に対応するためには「ある程度、先を読んだ研究で将来を想定して準備を整えておく必要がある」(同)と考えた。
さらに、所内からアイデアを引き出し、それを議論しながら取り組むべきテーマに落とし込んでいくことで、皆のベクトルを一致させる狙いもある。新たな試みは研究者の士気向上と、交通研の活性化に役立てていく。
こうした取り組みは2021年度に本格的にスタートさせる。現在、寄せられたアイデアを一つひとつ検証している段階という。交通研単独でのリソースは限られるが、大学に加え、さまざまな研究機関との連携も視野に入れており、効率的な研究の仕組みにも取り入れていきたい考え。
積極的に他の研究者と交わる機会にもつなげ、「ユニークなことを行っていると多くの人に知ってもらう」(同)ことで、交通研の認知度を高め、新たに優秀な研究者を招けるプラスのスパイラルの実現を目指す。
ただ、「最終的に社会に役立つ仕事がわれわれの使命」(同)と、基準化や審査など従来からの業務にも力を注ぐ。
昨年6月に予定していた「50周年記念講演会」は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて延期。11月に例年実施している「交通安全環境研究所フォーラム」と組み合わせる形で、初のオンライン開催に切り替えた。
異例づくしの開催となる中でも、当日のアクセス数は昨年のフォーラムの参加人数を上回る成果を残した。これは半世紀にわたって歴史を刻んできた交通研に対する自動車業界の期待や信頼の高さの裏付けといえよう。
100年に1度の変革期を迎えている日本の自動車産業が、次代でもイニシアチブを取り続けていくためにも、交通研が今後、どのように変革していくか、注目を集めそうだ。
| カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |
|---|---|
| 対象者 | 自動車業界 |
日刊自動車新聞12月23日掲載











